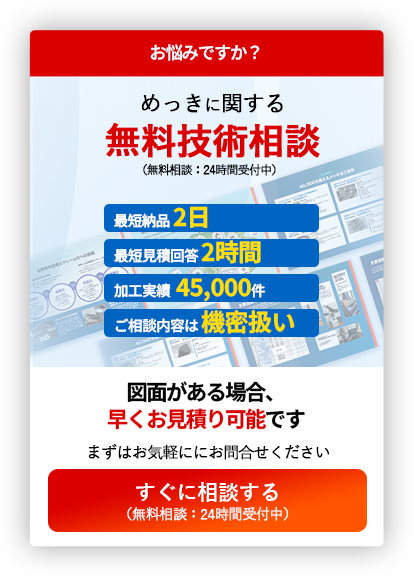めっきQ&A
FAQ
-
 三和メッキ工業株式会社HOME
三和メッキ工業株式会社HOME
- めっきQ&A
- 電解着色とアルマイト処理の違いは何ですか?
電解着色とアルマイト処理の違いは何ですか?
1.アルマイト処理(陽極酸化処理)
・目的:アルミニウムの表面に人工的に強固な酸化皮膜(酸化
アルミニウム:Al₂O₃)を生成させることで、耐食性、耐摩耗性、
硬度、絶縁性を向上させることが主な目的です。
装飾性も副次的な目的となります。
・原理:アルミニウムを陽極(プラス極)として電解液(硫酸や
シュウ酸など)に浸し、電流を流すことで、電気分解によって発生
する酸素とアルミニウムが反応し、表面に酸化アルミニウムの皮膜が
形成されます。この皮膜は、微細な孔(ポア)を持つ多孔質構造を
しています。
・色:基本的に無色透明またはアルミニウム合金の種類や電解条件に
よって自然発色(銀色に近い色や、わずかに灰色がかった色など)する
ことがありますが、この時点では着色は主目的ではありません。
・その後の処理:形成された多孔質皮膜は、着色や耐食性向上のための
後処理(封孔処理など)が可能です。
2.電解着色(二次電解着色)
・目的:アルマイト処理によって形成された酸化皮膜の微細孔を利用し
て、アルミニウムに着色することが主な目的です。
・原理:アルマイト処理が完了したアルミニウムを、さらに別の溶液
(スズやニッケルなどの金属塩を含む溶液)に浸し、再度電解処理を
行います。
この二次電解によって、酸化皮膜の微細孔の中に金属粒子やその酸化物
が析出し、光の干渉によって色が見えるようになります。
・色:ステンカラー、シャンパンゴールド、ブラック、ブロンズなど、
安定した多様な色調を出すことが可能です。析出させる金属の種類や
量によって、色の濃淡を調整できます。
●特徴:
・耐候性に優れる:染料着色(後述)に比べて、紫外線による退色や
変色が起こりにくいため、屋外で使用される建材などに広く用いられます。
・色ムラが少ない: 安定した着色が可能で、色ムラが発生しにくい特徴が
あります。
アルマイト処理は「皮膜を形成する」ことが目的であり、その皮膜は
透明または自然発色です。
電解着色は、アルマイト処理でできた「皮膜に着色する」ことが目的で
あり、金属粒子の析出によって発色させます。