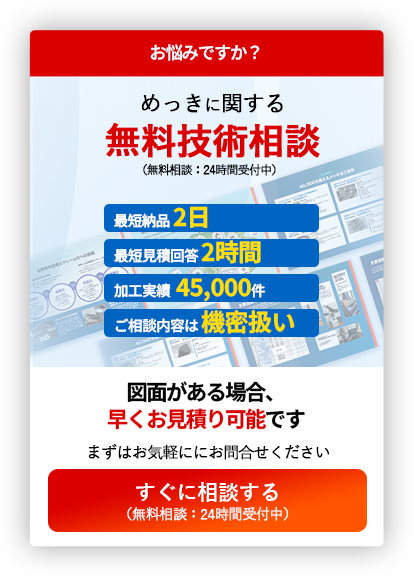めっきQ&A
FAQ
-
 三和メッキ工業株式会社HOME
三和メッキ工業株式会社HOME
- めっきQ&A
- 陽極酸化処理でカラーになるのは?
陽極酸化処理でカラーになるのは?
陽極酸化処理でカラーになる主な金属は以下の通りです。
アルミニウム (Al)
チタン (Ti)
タンタル (Ta)
ジルコニウム (Zr)
これらの金属は、陽極酸化処理によって表面に透明な酸化皮膜が
形成されます。
この酸化皮膜の厚さを制御することで、光の干渉現象(シャボン玉
やCDの表面が虹色に見えるのと同じ原理)によって様々な色を発色
させることができます。これを「構造色」と呼びます。
●発色の原理
・酸化皮膜の生成:
陽極酸化処理では、金属を陽極(+極)とし、電解液中で電気を流す
ことで、金属表面が酸化され、薄い透明な酸化皮膜が生成されます。
・光の干渉:
この透明な酸化皮膜に光が当たると、光の一部は皮膜の表面で反射し、
残りの光は皮膜を透過して金属基材の表面で反射します。
この2つの反射光が互いに干渉し合うことで、特定の色が強調された
り打ち消されたりして、様々な色が見えるようになります。
・膜厚と色の関係:
酸化皮膜の厚さを変化させることで、干渉する光の波長が変わり、
見える色も変化します。
印加する電圧を調整することで、酸化皮膜の厚さを精密に制御し、
目的の色を出すことができます。
●アルミニウムの場合
アルミニウムの陽極酸化処理(アルマイト処理)では、生成される酸化
皮膜は通常無色透明です。
アルミニウムをカラーにする方法は主に2つあります。
・染料による着色:
陽極酸化処理で形成された多孔質の酸化皮膜に染料を吸着させることで、
様々な色に着色できます。その後、封孔処理によって染料を皮膜内に
閉じ込め、色の耐久性を高めます。
・自然発色・電解着色:
アルミニウム合金の種類や電解条件(電解液の種類・濃度・温度、電流
密度など)を組み合わせることで、染料を用いずに自然に発色させる方法
や、金属塩を含む浴に浸して電流を流すことで金属を析出させて発色させ
る方法もあります。
●チタン、タンタル、ジルコニウムの場合
これらの金属は、アルミニウムとは異なり、陽極酸化処理によって生成
される酸化皮膜そのものが構造色を発します。
そのため、染料を使わずに電圧によって皮膜の厚さを制御するだけで、
様々な鮮やかな色を出すことができます。