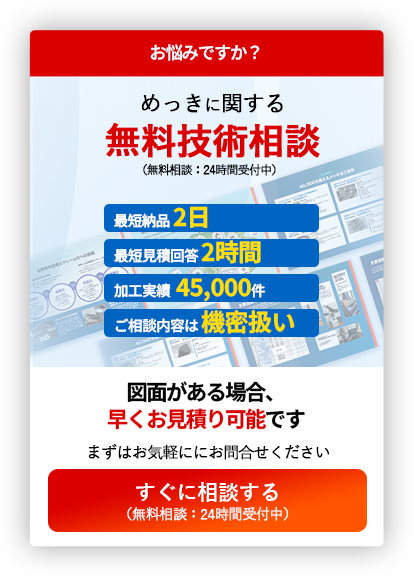めっきQ&A
FAQ
-
 三和メッキ工業株式会社HOME
三和メッキ工業株式会社HOME
- めっきQ&A
- クロムメッキの欠点は何ですか?
クロムメッキの欠点は何ですか?
クロムメッキは、その優れた特性から広く利用されていますが、
いくつかの欠点も存在します。
1. マイクロクラックの存在
クロムメッキ皮膜には、必ずマイクロクラック(微細なひび割れ)が
存在します。
これは、クロムの結晶構造と製造プロセスに起因するものであり、
避けることができません。
・耐食性の限界:
このマイクロクラックが下地まで貫通している場合、そこから腐食因子
(水分、酸素、塩分など)が侵入し、下地金属を腐食させる原因となります。
これが、クロムメッキが「錆びる」と言われる主な理由です。
・解決策:
この欠点を補うために、通常は耐食性の高いニッケルメッキを下地と
して施す「ニッケルクロムメッキ」が一般的です。
2.メッキの均一性
クロムメッキは、「電気メッキ」の一種であり、電流の分布によって
メッキの析出厚みが不均一になりやすいという欠点があります。
・複雑な形状に不向き:
電流が集中しやすい角や突起部分には厚くつき、逆に電流が流れにくい
凹んだ部分には薄くしかつきません。
このため、複雑な形状の部品に均一なめっきを施すことが困難です。
・解決策:
これを補うために、メッキ治具を工夫したり、補助電極を使用したり
するなどの対策が取られますが、限界があります。
3.溶接性の悪さ
クロムメッキは、非常に硬く、融点が高い(約1857℃)ため、溶接性が
非常に悪いという欠点があります。
・溶接不可:
一度クロムメッキを施した部品は、基本的に溶接ができません。
溶接しようとすると、メッキ層が邪魔をして溶接不良を起こしたり、
溶接部周辺のメッキが変質したり、剥がれたりします。
4.高温酸化による変色が起こります。
200〜400℃で酸化膜が成長し、青色や褐色に変色します。
5.摩耗粉発生の可能性があります。
摺動部では長期使用で硬質クロムが剥離し、摩耗粉が発生。
精密機構では不具合原因になる可能性があります。
6.耐食性限界
海水・酸・アルカリに長期曝露されると腐食が進行します。
特に海洋構造物や化学プラントでは単層クロムは不向きです。