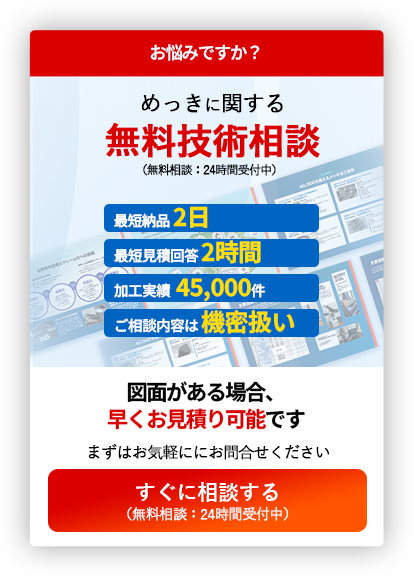めっきQ&A
FAQ
-
 三和メッキ工業株式会社HOME
三和メッキ工業株式会社HOME
- めっきQ&A
- 溶融亜鉛メッキと電気亜鉛メッキの違いは?
溶融亜鉛メッキと電気亜鉛メッキの違いは?
亜鉛メッキには各種の方法があり、それぞれの目的や特性、
コストなどを考慮し選択されています。
電気メッキ法のメカニズムをミクロ的な見方をすると、
水溶液中の金属イオンを電気エネルギーによって一つ
一つ金属を変えて、物の表面にめっき金属を超高速で積み
重ねていく原子レベルでの成膜加工技術であると言えます。
従って、厚膜化が不利で、比較的薄い亜鉛メッキの厚さと
亜鉛メッキの腐食を防ぐクロメート皮膜との組み合わせで
耐食性を発揮します。
更に、耐食性の向上を図るため、各種のクロメート皮膜や
高耐食性亜鉛合金メッキの開発など行われ自動車部品を
中心に採用されています。
一方、溶融メッキ法は、被メッキ物を溶融金属中に浸漬して
被メッキ物表面に溶融金属を付着させ、冷却して金属を被覆
する方法であり、厚膜化が可能です。
厚さは、一般に亜鉛鉄板で8〜20μm、構造物で75〜125μm
程度です。
防錆メッキである、亜鉛メッキの防錆機構は、犠牲防食作用
(亜鉛が腐食することによって鉄の錆の発生を防ぐ)
であるため、長期間に渡って防錆力を保つにはメッキ厚さ
が厚ければ厚い法が良いことになり、手法上からメッキ厚さを
十分に確保出来る溶融亜鉛メッキが有利となります。
従って、溶融亜鉛メッキは、主に、重量物や屋外の構造物
(橋、鉄塔、外壁、建築部材など)などに亜鉛メッキは
単独又は塗装との組み合わせによる重防食を行う必要が
あるものに適用されます。
逆に数10μm以下の場合には、クロメート皮膜の防錆力が
付加された電気亜鉛メッキの方が有利です。
このように、メッキ法の基本的な手法や原理からくる適用や
限界、皮膜の性質等に違いが生じることから、単純に防錆力の
比較は出来きず、防錆メッキの利用目的によって溶融亜鉛メッキ
と電気亜鉛メッキとの使い分け方をすることが肝心です。
JIS H 8614 溶融亜鉛メッキの解説の項に、亜鉛メッキの
付着量と推定対数年数との関係が暴露環境別に提示されて
います。