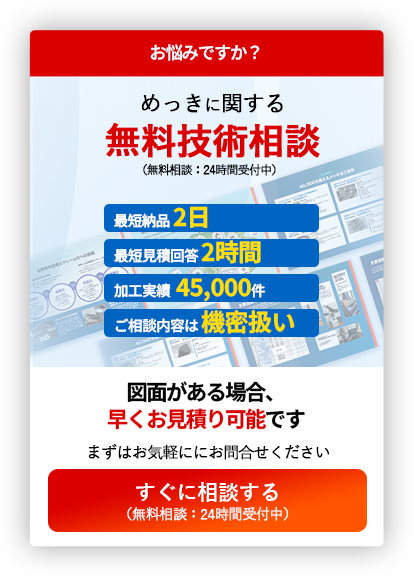めっきQ&A
FAQ
-
 三和メッキ工業株式会社HOME
三和メッキ工業株式会社HOME
- めっきQ&A
- 材質番号により硬質アルマイト処理後の色違いが発生する理由は?
材質番号により硬質アルマイト処理後の色違いが発生する理由は?
材質番号によって硬質アルマイト処理後の色違いが発生
する理由は、主に合金に含まれる成分の差が、皮膜の生成
や自然発色に影響するからです。
●硬質アルマイトの自然発色
硬質アルマイト皮膜は、無着色でも膜厚が厚くなるにつれて
自然に発色します。
この自然発色の色は、素材に含まれる微量な成分によって
決まります。
●主要な合金成分と色の関係
1.ケイ素(Si)
ケイ素を多く含む合金(例:A4000系やアルミ鋳物)は、アル
マイト処理中にケイ素が皮膜内に取り込まれ、濃いグレーや
黒っぽい色になりやすいです。
皮膜の成長が阻害されるため、均一な色合いになりにくいこと
もあります。
2.銅(Cu)
銅を多く含む合金(例:A2000系)は、皮膜が褐色や濃い茶色に
自然発色しやすいです。
3.亜鉛(Zn)
亜鉛を多く含む合金(例:A7000系)は、皮膜が褐色から白っぽい
グレーに発色することがあります。
4.マグネシウム(Mg):
マグネシウムを多く含む合金(例:A5000系)は、比較的発色が
少なく、元の銀色に近い色に仕上がりやすいです。