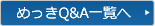PLATING PROCESSES AND TECHNIQUES
-
 三和メッキ工業株式会社HOME
三和メッキ工業株式会社HOME
- めっき加工
めっき加工
めっき加工とは電気の力や置換反応を利用して行う表面処理技術のことで、金属や非金属の樹脂などの素材表面に薄い金属皮膜をつけ、防食性や強度、外観性、機能性をもたせることができます。めっき加工の歴史は古く、現在はさまざまな種類のめっき加工が存在します。この記事では、めっき加工の種類やそれぞれの特徴について紹介します。
目次
めっき加工とは
めっき加工とは表面処理の一種で、水溶液中で電気の力や置換反応を利用して、金属、非金属の樹脂といった素材の表面に薄い金属皮膜をつけることで防食性や強度、外観性、機能性をもたせる技術のことをいいます。
めっき加工の種類はいくつもありますが、湿式めっきと乾式めっきの2つに大別できます。湿式めっきは、薬液(めっき液)を使って化学反応で皮膜を生成するめっきのことで、乾式めっきは薬液(めっき液)を使わずに物理的な方法で皮膜を生成するめっきです。この2種類以外には、陽極酸化処理、化成処理などもあります。[1]
めっき加工の歴史
めっき加工の歴史は古く、古代文明の時代から利用されています。約3500年前である紀元前16世紀に北部メソポタミア(現在のイラク)で鉄器などに錫(すず)めっきが行われました。日本では、752年の奈良の大仏建立の際に、水銀に金を混ぜ合わせた合金(金アマルガム)が表面に塗布されています。[2]
めっき加工の特徴
めっき加工では、素材本来の性質に新たな性質を付加することによって、次のような特徴を素材に加えることができます。
- 外観性の向上
- 耐食性の向上
- 耐摩耗性の向上
- 電気伝導性の向上
- 潤滑性の向上
- 電気・磁気特性の向上
- 熱特性の向上
- 光沢などの光特性の向上
湿式めっきとは
湿式めっきは薬液(めっき液)を使って化学反応で皮膜を生成するめっきの総称で、めっき方法として電気めっきと無電解めっきの2つがあります。
電気めっき
電気めっきとは、電気分解(電解)の応用で、めっき液中の金属イオンを電気を使って還元することにより、金属皮膜を生成させる技術のことをいいます。
電気めっきを行う種類としては、次のものがあります。
電気めっきの原理
電気めっきの原理は、金属イオンが存在する電解質水溶液に、陰極(めっきしたい素材)と陽極の2つの電極に電気を流し、陰極において還元反応を生じさせます。


電気めっきの歴史
電気めっきが発明されたのは、1805年です。それまでの長い間、めっき技術はアマルガム法か無電解めっき法しかありませんでした。しかし電気めっきの発明以降は、次々と開発が進み、さまざまなめっきが誕生するようになりました。
亜鉛めっき
亜鉛めっきとは、鉄素地を亜鉛めっき浴に浸漬して電解することによって亜鉛皮膜を生成する方法です。亜鉛めっき上に不動態膜が生成されることで、防錆効果が高くなる性質があるため、主に鉄鋼に使われています。めっきをしただけでは、亜鉛めっき皮膜が酸化し腐食してしまうため、クロメート処理を施して鉄素地の耐食性を向上させる必要があります。
特徴
亜鉛めっきの特徴は次の通りです。
- 耐食性が高い
- 導電性が高くなる
- はんだ付け性が良好である
亜鉛めっきの工程
亜鉛めっきの工程は次の通りです。
- 脱脂
- 電解脱脂
- 酸洗
- めっき
- 硝酸浸漬
- 各種クロメート処理
- 乾燥
ニッケルめっき
ニッケルめっきとは、金属素地をニッケルめっき浴に浸漬し電解することによってニッケル皮膜を生成させるめっきのことをいいます。錆びにくく、鉄に近い性質を持っていますが、空気中の湿気に対しては鉄よりも安定していることから、装飾、防食の両面に利用されています。
特徴
ニッケルめっきの特徴は次の通りです。
ニッケルめっきの工程
ニッケルめっきの工程は次の通りです。
- 脱脂
- 電解脱脂
- 酸活性
- ニッケルめっき
- 乾燥
クロムめっき
クロムめっきとは、金属素地の下地にニッケルめっきを行い、クロムめっき浴に浸漬し電解することによってクロム皮膜を生成させるめっきのことをいいます。
クロムめっきを大別すると「装飾クロムめっき」「硬質クロムめっき」の2つがあります。この2つは同じクロムめっきと呼ばれるものですが、膜厚によって区別され、一般的にクロムめっきと呼ぶ場合は「装飾クロムめっき」を指します。
特徴
装飾クロムめっきの特徴は次の通りです。
- 耐食性が高い
- 光反射性が高い
- 熱反射性が高い
クロムめっきの工程
クロムめっきの工程は次の通りです。
- 脱脂
- 電解脱脂
- 酸活性
- ニッケルめっき
- クロムめっき
- 乾燥
硬質クロムめっき
硬質クロムめっきは金属素地にダイレクトに電解してクロム皮膜を1µm以上生成させるめっきのことをいいます。硬質クロムめっきは厚いめっきを施すことにより、硬度と耐摩耗性が良くなるため、機械部品や金型など工業製品によく使われています。
特徴
硬質クロムめっきの特徴は次の通りです。
- 硬度が高い
- 耐摩耗性がある
- めっき膜厚を厚く出来る
クロムめっきの工程
硬質クロムめっきの工程は次の通りです。
- 脱脂
- 酸活性
- 陽極処理(エッチング)
- 硬質クロムめっき
- 乾燥
金めっき
金めっきとは、金属素地を金めっき液浴に浸漬し電解することで、金皮膜を生成させるめっきのことをいいます。
金は外観が美しい点を持つ以外にも、電気や熱をよく伝える性質やはんだづけ性にも優れています。
特徴
金めっきの特徴は次の通りです。
金めっきの工程
金めっきの工程は次の通りです。
- 脱脂
- 酸活性
- ニッケルめっき
- 金めっき
銅めっき
銅めっきとは、各種めっき処理の下地めっきで、銅めっき液浴に浸漬し電解することで銅皮膜を生成させるめっきのことをいいます。
金属としての銅は、電気伝導性と熱伝導性、延性に優れています。
特徴
銅めっきの特徴は次の通りです。
- 熱伝導率が高い
- 耐菌性がある
- 電磁波シールド性に優れる
- 電気伝導率が高い
銅めっきの工程
銅めっきの工程は次の通りです。
- 脱脂
- 電解脱脂
- 酸活性
- ニッケルストライク
- 銅めっき
- 乾燥
無電解めっき
無電解めっきとは、電気を用いることなく、溶液中の金属イオンが還元剤の働きで電子を受け取って還元析出するめっきのことをいいます。均一にめっきがつくため形状が複雑でもめっきがつきやすいのが特徴です。
原理
金属のイオン化傾向を利用した置換反応により、溶液中で電位の卑な金属上に電位の貴な金属を析出させます。

歴史
1835年にドイツで開発されたガラス面に銀を析出させる銀鏡反応が、無電解めっきの最初とされています。
無電解ニッケルめっき
無電解ニッケルめっきとは、電気を流さずめっき浴中で化学的還元反応を利用してリンとニッケルを析出させるめっき処理のことをいいます。無電解ニッケルめっきで使われるめっき液には、還元剤として次亜リン酸ナトリウムが使用されることから、析出する皮膜にはリンが含まれます。そのため無電解ニッケルめっきには、一般的なニッケルめっきとは異なるさまざまな特性があります。
特徴
無電解ニッケルめっきの特徴は、次の通りです。
- 耐食性が高い
- 皮膜が均一
- 複雑な形状にもめっきが出来る
- 寸法精度を維持できる
- 硬度が高い
- 不導体(絶縁体)にもめっきできる
無電解ニッケルめっきの工程
無電解ニッケルめっきの工程は次の通りです。
- 脱脂
- 電解脱脂
- 酸活性
- 無電解ニッケルめっき
- 乾燥
置換めっき
置換めっきとは、金属塩水溶液中で置換反応によって金属皮膜をつけるめっきのことをいいます。
原理
外部からの電気エネルギーの供給や還元剤の働きなしに、金属のイオン化傾向を利用した置換反応により、溶液中で電位の卑な金属上に電位の貴な金属を析出させます。

特徴
置換めっきでは、素材の表面が完全にめっきされてしまうと、電子の供給ができなくなり、めっきができなくなるため、得られるめっきの厚さには限界があります。
そのため、皮膜が薄く耐食性は高いが、密着性が悪いという特徴を持ちます。
溶融めっき
溶融めっきとは、融点の高い金属素地を、融点の低い被覆金属を溶解させた液中に浸漬して表面に融着、浸透させるめっきのことをいいます。
原理
高温度で溶融している金属の中に製品を浸漬して引き上げ、製品の表面に溶融金属の皮膜を形成させます。
歴史
1742年フランスの科学者P.J. Malouinが発明したと言われています。
溶融亜鉛めっき
溶融亜鉛めっきとは、450℃程度の溶解した亜鉛めっき槽に製品を浸漬し冷却するめっきのことをいいます。
製品の影になる部品へのめっき処理が可能なため、大きな製品に向いていますが、素材に反りが発生するため精密部品への処理は向いていません。
特徴
溶融亜鉛めっきの特徴は次のようなものがあります。
- 耐食性が高い
- 密着性が高い
- 剥離しにくい
- 膜厚を厚く処理出来る
- 塗装との密着性がよい
乾式めっきとは
乾式めっきとは、真空中でめっきする方法で真空容器内を真空ポンプで高真空にして、金属を高温で蒸気にし、素材を被覆するめっきのことをいいます。
真空蒸着
真空蒸着とは、気体中もしくは真空中にて材料表面に金属膜を生成する技術です。真空中で金属を加熱すると、金属が蒸発します。その蒸発分子を、蒸気温度より低温の基材に付着させると、表面で蒸気が凝縮し、薄膜を形成します。この薄膜はきわめて薄く、通常0.05〜0.1μm程度です。表面の光沢は、基材の粗さや蒸着時の雰囲気で異なります。
原理
容器内を金属蒸気で満たし、あらかじめ樹脂コーティング(塗装)した被処理物を金属で被覆する技術で単純に金属の気体分子を作って、被処理物に付着させます。

歴史
1857年に電気分野のマイケル・ファラデー(ファラデーの法則)が最初に行ったと言われています。
特徴
真空蒸着の特徴は、次の通りです。
- 皮膜が薄い
- 装飾性がある
- 帯電防止が出来る
スパッタリング
スパッタリングとは、成膜したい金属をイオン化した不活性ガスで、はじき飛ばして被処理物に付着させるめっきのことをいいます。
原理
物質にイオン等を高速で衝突させることにより、分子が叩き出される現象を利用します。

歴史
1950年代後半に、ドイツにおいて耐摩耗材としての炭化チタン膜が作製されたとされています。
特徴
スパッタリングの特徴は、次の通りです。
- 基板や基材への付着率が大きい
- 皮膜を均一に処理出来る
- 密着性が高く強い結晶性の高い皮膜を作れる
イオンプレーティング
イオンプレーティングとは、真空容器中に蒸発した金属粒子の一部をイオン化して薄膜を形成させるめっきのことをいいます。
原理
蒸発粒子をプラズマ中を通過させることで、プラスの電荷を帯びさせ、基板にマイナスの電荷を印加して蒸発粒子を引き付けて堆積させ膜を作成します。樹枝状結晶などの生成はイオンの衝撃で妨げられ、等方的な結晶組織になり、膜の密着度が高く、化合物皮膜も得られます。

歴史
宇宙開発技術の一環として、アメリカで発明された技術です。
特徴
イオンプレーティングの特徴は、次の通りです。
- 密着性がよい
- 耐摩耗性が有る皮膜を作れる
- 緻密な成膜が可能
化学気相めっき(CVD法)
化学気相めっき(CVD法)とは、常圧あるいは減圧下でハロゲン化金属などのガスを加熱した素材面で分解または置換、あるいは水素を送って還元させてめっき皮膜を得るめっきのことをいいます。
原理
成膜したい元素を含む気体を基板表面に送り、化学反応、分解を通して成膜させます。
特徴
化学気相めっき(CVD法)の特徴は、次の通りです。
- 凹凸がある基板でも均一な皮膜を作れる
- 無機物・有機物への成膜が可能
- 量産性に優れる
陽極酸化処理
陽極酸化処理とは、電解溶液中で金属を陽極として通電させることで、表層に酸化皮膜を成長させる処理のことをいいます。
原理
金属表面を陽極(+)で電解処理して酸化皮膜を人工的に作ります。
アルマイト処理
アルマイト処理とは、アルミニウム表面の陽極酸化皮膜を作る処理で、人工的にアルミニウム表面に厚い酸化アルミニウム皮膜を作ることにより耐食性・耐摩耗性の向上、美観性やその他の機能を付与する処理のことをいいます。
原理
電解質溶液中にアルミニウムを浸し、アルミニウムを陽極(正極)として通電させることにより、酸化されて陽イオンとなり、溶液中に溶解し発生した酸素と化合して酸化アルミニウムの被膜が生成されます。
歴史
1929年に理化学研究所にて発明されました。
特徴
アルマイト処理の特徴は次のようなものがあります。
- 耐食性がある
- 硬度や耐摩耗性がある
- 電気絶縁性が高くなる
- 着色することができる
- 美観性が向上する
アルマイト処理の工程
アルマイト処理の工程は次の通りです。
- 脱脂
- エッチング
- 酸活性
- アルマイト処理
- 封孔処理
- 乾燥
化成処理
化成処理とは表面処理の形式のひとつで、素材、特に金属の表面に処理剤を作用させて化学反応を起こさせる処理のことをいいます。
黒染めっき
黒染めっきとは、鉄の表面の化学変化をアルカリ処理することで黒錆と呼ばれる四三化鉄の酸化皮膜を作る処理です。
特徴
黒染めっきの特徴は、次のようなものがあります。
- 耐食性がある
- 剥がれない皮膜を作ることが出来る
- 光沢のある黒色皮膜を作れる
黒染めっき(処理)の工程
黒染めっき(処理)の工程は次の通りです。
- 脱脂
- 酸処理
- 黒染めっき(処理)
- 防錆油
リューブライト処理
リューブライト処理とは、リン酸マンガン皮膜処理のことであり、黒色の皮膜でリン酸塩処理としてマンガン皮膜を析出させる処理のことをいいます。
特徴
リューブライト処理には次のようなものがあります。
- 耐食性がある
- 耐摩耗性がある
- 絶縁皮膜を作れる
- 鋳物の材質に適している
- 油の保持性に優れる
- 潤滑性がある
- 塗装の下地に適している
リューブライト処理の工程
リューブライト処理の工程は次の通りです。
- 脱脂
- 酸処理
- 表面調整
- リューブライト処理
- 防錆油
個人さまからのめっき加工について
個人からのめっき加工ご依頼について
ご依頼時にお伺いしたいのは材質です。
めっき加工が出来るかどうかは材質で決まります。
次にどのようなめっき加工を処理したいのかをお教え頂くことになります。
プラスチックへのめっき加工対応について
プラスチックへのめっき加工は非常に難しく一般的な方法では処理することが出来ません。
対応出来たとしても専用のめっき加工前処理設備等が必要になります。
ゴールドのめっき加工について
当社の場合、ゴールドのめっき加工は金めっきにあたります。
24Kめっきを処理をしますが素材や大きさに制限があります。
金めっきは軟質ですので傷がつきやすいというデメリットがあります。
めっき加工の料金について
お問合せで一番多いのが、めっき加工料金ついてです。
適正な料金をお知らせするのには、材質等を見極める必要があります。
当社で対応出来ないめっき加工は他社をご紹介させて頂く場合があります。
上記の内容をお教え頂ければ詳細のお見積をご提案させて頂きます。
当社の場合、はがきサイズの製品に亜鉛めっきをした場合、¥1,000円からになります。
アクセサリーへのめっき加工について
アクセサリーのめっき加工は現在のめっき加工と材質を明確にして頂く必要があります。
お解りになられない場合には、当社にアクセサリーをお送り頂き判断させて頂きます。
まとめ
めっき製品は、身近な生活用品やアクセサリー、自動車や航空機など、日常のあらゆるところで使われています。めっき加工は、素材に金属をつけることにより、外観性の向上や錆びないようにすること、硬度などの機能特性を付与し、あらゆる産業界で利用されている技術です。
めっき加工に関する技術レポート
クリックするとPDFファイルが開きます。
- 各種表面処理と主な特性をまとめた表です。
◎が一番効果が高く、装飾、防錆、耐摩耗性などで区分してあります。 
- めっきによる水素脆性は前処理やめっき加工の過程で被めっき物が水素を吸蔵して脆くなる現象をいいます。その内容をレポートでまとめています。

- 工業用めっきの各種特性を機械的特性、電気的特性、光的特性、熱的特性、物理的特性、化学的特性/その他の特性で分けた内容をレポートにしてまとめました。

- 接点部品へのめっきとして要求される事項は様々です。
通常接点素材として導電性、バネ性、加工性のよいリン青銅や黄銅、その他の金属上にめっきを行って使用することが多いです。
接点めっき皮膜に用いられるものとしては電気めっきが一般的に多いですが、無電解めっきも使用されるようになっています。
表にて接点めっき皮膜の長所と短所をまとめました。 
- 金型を対象とした表面処理の種類と特徴についてまとめました。
金属に採用される表面処理技術には、湿式と乾式法があります。
金型の種類、材質、形状、目的によって適、不適があることを理解する必要があります。 
- ビッカース硬さ、ロックウェル硬A、B、Cスケールプリネル硬さの硬度換算表です。
めっき硬度については、ビッカース硬度を一般的に使用します。 
- 高張力鋼や高炭素鋼を酸処理すると、水素を吸蔵して水素脆化を引き起こすことが知られています。
酸濃度が高い場合は短時間で水素脆性を起こしやすくなります。
酸でめっき剥離を行う場合の対策をレポートでまとめました。 
- スパッタリングとは、本来は高速のイオン等がターゲットに衝突する時、ターゲット構成する原子がたたき出させる現象を指しています。
スパッタリング法のメリットとデメリットをまとめました。 
- ドライプロセスには、真空プロセスと常温とプロセスがあります。
それぞれのプロセスは成膜による表面コーティングと表面の化学構造を改質するプロセスに分けることが出来ます。
その概要をレポートにしてまとめました。 
- 不動態とは、金属が電気化学列では卑な位置にあるにも関わらず、非常に遅い速度で腐食する金属の状態をいいます。
不動態化現象についてレポートでまとめました。 
- 湿式めっき法は、外部直流電流を用い水溶液中の金属イオンのカソード還元により金属薄膜を形成する電気めっき法と外部直流電流を用いず水溶液中に添加した還元剤の酸化反応に伴い供給される電子により金属を形成する無電解めっき法があります。
電気めっきと無電解めっきの原理などを含めレポートにまとめました。 
- 物質の表面に改質して違った機能を得る目的で、今日では各種の界面科学を用いて表面改質処理が研究されています。長い表面処理技術の中で最近になり最も注目されてきている処理技術として複合めっきがあげられます。その複合めっきの概要と特性をレポートにてまとめました。

- 防食めっきは、装飾めっきと並んで、めっき技術の原点です。
実用的な金属素材である、鉄・アルミニウムなどは、構造物や機械部品、あるいは身近にあるものまで広く利用されているが、素材を錆から守るために何らかの表面処理が施されています。
その一つの方法として古くから防食性、装飾性を兼ね揃えた方法として電気めっきあるいは化成処理などの手法が利用されてます。
腐食とめっき(化成処理)による防食内容をレポートにてまとめました。 
- 無電解めっきは広い意味では外部電源を用いずに金属めっき膜を成膜する技術と定義されてます。
無電解めっきは自己触媒めっきとも呼ばれ、いろんな金属を析出させます。
その無電解めっきの概要をレポートでまとめています。 
- 電気めっき浴の構成成分は、金属塩、電導度塩、アノード溶解促進剤、錯化剤、皮膜の外観と物性を調整する添加剤などから構成されてます。
無電解めっき浴では、金属塩に加えて還元剤、錯化剤、pH緩衝材および安定剤が必須であるという特徴を持ちます。
各めっき浴の構成成分とその役割をレポートでまとめています。 
- 適正なめっき加工を行い、お客様のニーズに見合った品質にて納品するためには、いろんな手法があり選択と注意が必要です。
一般的なめっき手法をレポートにてまとめました。 
- クロメート処理は、リン酸塩処理とならぶ化成処理の最も代表的な処理方法です。
電気亜鉛めっき後にクロメート処理を行い耐食性を向上させるのが一般的です。
クロメート処理の種類と方法などをレポートにてまとめました。 
- 電気めっきの長所と短所をまとめました。

脚注
- [1]Wikipedia:めっき
土井正:よくわかる最新めっきの基本と仕組み「第3版」 秀和システム
中出卓男:J-STAGE 2018年67巻11号 - [2]Wikipedia:めっき
トコトンやさしいめっきの本 日刊工業新聞社 - [3]絵とき「めっき」基礎のきそ プレーティング研究会
- [4]石島 三郎 J-STAGE 965年33巻10号
絵とき「めっき」基礎のきそ プレーティング研究会 - [5]トコトンやさしいめっきの本 日刊工業新聞社
- アルマイトとメッキの違いは何ですか?
- 表面処理とは?
- 酸化被膜とはわかりやすく説明するとどのようになるのか?
- 表面処理にはどのような金属に対応出来るのか?
- 表面処理加工とは?
- アルミニウムの欠点は?
- 各メッキ皮膜の摩耗係数
- 各メッキ皮膜の摩耗量
- 各メッキ皮膜の剥離性
- 各種メッキの塩水噴霧試験結果について
- 各メッキ加工の摩耗性と潤滑性の関係は?
- 食品衛生法適合試験検査について
- 種々の素材の前処理とメッキ技術の関係は?
- メッキ実績表と素材との関連性は?
- 各メッキ皮膜耐食性試験結果はあるのか?
- メッキ浴の構成成分と添加剤の作用機構とは?
- 昔の表面処理の記号は?
- スズメッキとは?
- 表面状態を表す記号は?
- チタン等、難材へのメッキは出来るのか?
- 無電解メッキの長所と短所は?
- 無電解メッキ皮膜の耐摩耗性・耐食性は?
- 装飾メッキとその歴史とは?
- メッキ手法のラック法とバレル法の違いは?
- 黒色皮膜のメッキとは?
- 昔のメッキ規格はどのような記号なのか?
- 個人でアクセサリーのメッキ加工を依頼することは可能か?
- 個人で依頼した場合のメッキ加工料金を教えてもらうことは可能か?
- 個人でゴールドのメッキ加工を依頼したいが対応可能か?
- 個人でプラスチックへのメッキ加工を依頼したいが対応可能か?
- 個人のメッキ加工依頼時に伝える必要がある内容とは?
- 表面処理を英語では?
- クロメート処理を英語では?
- メッキ引っ掛け治具からめっきが剥離することはあるのか?
- メッキ治具の接点からメッキが剥離することはあるのか?
- Black dyeとは?
- Blackeningとは?
- 黒染めとパーカー処理は異なるのか?
- ニッケルメッキは自作出来るのか?
- 黒メッキは自作出来るのか?
- メッキ加工は自分で出来るのか?
- アルミに導電性のあるメッキをしたい場合には?
- アルミにメッキする場合の価格計算方法は?
- アルミに通電するメッキをしたい場合には?
- 亜鉛メッキとアルミの違いは?
- ユニクロメッキの価格は?
- 黒色無電解ニッケルメッキの価格は?
- 金メッキが剥がれる原因は?
- メッキ剥げれを補修出来るペンはないのか?
- 黒クロムメッキが剥がれる原因は?
- メッキの色はどのような種類があるのか?
- ステンレスにメッキ処理した製品を組むと腐食が発生する原因は?
- クロームメッキとメッキの違いは?
- メッキの錆落としを行う場合でおすすめは?
- メッキでの錆落としはピカールで可能か?
- 黒メッキは自作出来るのか?
- 錫メッキは、はんだ付けに適しているのか?
- メッキでハンダ付け性が良いめっきは?
- 金メッキではんだ付けが不良になる原因は?
- 電気メッキのjisは?
- JIS H 0401とは?
- 溶融亜鉛メッキのjis改正はいつされたのか?
- JIS H 8641とは?
- JIS H 8643とは?
- 無電解メッキの原理は?
- 無電解メッキの種類は?
- 電気メッキの種類は?
- 電解メッキと無電解メッキの違いは?
- メッキの種類の見分け方は?
- 金属メッキの種類は?
- 電解メッキの種類には何があるのか?
- 装飾メッキの種類には何があるのか?
- メッキの種類によって価格は変わるのか?
- 溶融亜鉛メッキを英語では?
- メッキ加工を英語では?
- 金メッキを英語では?
- 電解メッキを英語では?
- メッキが剥がれるの意味は?
- メッキと塗装の違いは?
- メッキの例としてどのようなものがあるのか?
- 電気メッキの原理は?
- メッキ液とは?
- 金属メッキとは?
- メッキの原理は?
- メッキ種類の一覧としてどのようなものがあるのか?
- 純金と水銀の関係について
- メッキを英語では?
- 純金鍍金とは?
- 鍍金工業とは?
- 鍍金、ときんとは?
- 鍍金の読みは?
- 電気メッキの呼び方は?
- 錫メッキの歴史は?
- メッキは何のため?
- メッキってどういう意味?
- メッキのJISは?
- メッキを化学的にいうと?
- メッキの種類にはどのようなものがあるのか?
- メッキを英語でいうと?
- メッキとは、わかりやすくいうと?
- メッキの基礎知識としてどのようなものと考えればいいのか?
- メッキを漢字では?
- 金属メッキ加工の仕組みは?
- メッキ加工の目的は?
- メッキ加工の材料は?
- メッキ加工の仕組みは?
- メッキ加工のデメリットは?
- メッキ加工をアクセサリーに出来るのか?
- メッキ加工の料金は?
- メッキしてあるアクセサリーの修理は可能か?
- アクセサリーにメッキしたが剥がれる原因は?
- アクセサリーにメッキ加工が出来る業者は東京にあるのか?
- ネックレスにメッキ加工した場合の料金は?
- アクセサリーに再メッキした場合は購入した時よりも安いのか?
- アクセサリーへのメッキ加工した場合の料金は?
- アクセサリーへの再メッキは自分で出来るのか?
- プラスチックにメッキ出来る会社はあるのか?
- プラスチックにメッキ塗装は可能か?
- absにメッキ加工は可能か?
- ABSにメッキを個人依頼することは可能か?
- プラスチック専用のメッキスプレーはあるのか?
- プラスチックにメッキする方法は?
- プラスチックにメッキ加工処理した場合の料金は?
- メッキ加工を神奈川県で個人にて依頼することは可能か?
- 再メッキは自分で出来るのか?
- バイクはメッキスプレーを使用して処理出来るのか?
- バイクにメッキ塗装は出来るのか?
- バイクにメッキ加工を自作出来るのか?
- メッキ加工は持ち込みで対応出来るのか?
- プラモデルにメッキ加工出来る業者はあるのか?
- メッキ加工は電気を使用するのか?
- 楽器のメッキ加工のやり方は?
- メッキ加工の個人価格は?
- クロームメッキは自作出来るのか?
- メッキの価格はどのように計算するのか?
- メッキ加工の料金で大阪の場合には?
- メッキで価格比較をしたい場合には?
- メッキ加工を個人で東京に依頼することは可能か?
- 再メッキの料金は?
- メッキ加工料金で千葉県は?
- メッキ加工料金で福岡は?
- ブラックメッキのメッキ加工料金は?
- メッキ加工料金で茨城の価格は?
- 自転車にメッキ加工した場合の料金は?
- メッキ加工の料金は、東京で幾らか?
- バイクにメッキ加工した場合の料金は?
- クロームメッキ加工とは?
- バイクのメッキ加工料金は?
- 銀メッキは自分で出来るのか?
- メッキ加工のスプレーはあるのか?
- アクセサリーに自分でメッキ加工は出来るのか?
- 金メッキ加工は自分で出来るのか?
- 自分でクロムメッキは出来るのか?
- アクセサリーにメッキ加工は出来るのか?
- プラスチックにメッキ加工は出来るのか?
- メッキ加工はバイクに出来るのか?
- メッキ加工業者とは?
- メッキ加工のやり方は?
- メッキ加工で個人の価格は?
- メッキ加工の料金は?
- メッキ加工は自分で出来るのか?
- 三和メッキとしてどのようなメッキ加工が可能か?
- メッキの特徴とは?
- アルミニウムに黒無電解ニッケルめっきは可能か?
- 鍍金とは?
- 亜鉛ダイカストへのメッキ方法は?
- かじり現象とは?
- AM-O2とは?